今回は、決算書における「分配可能額」について解説します。
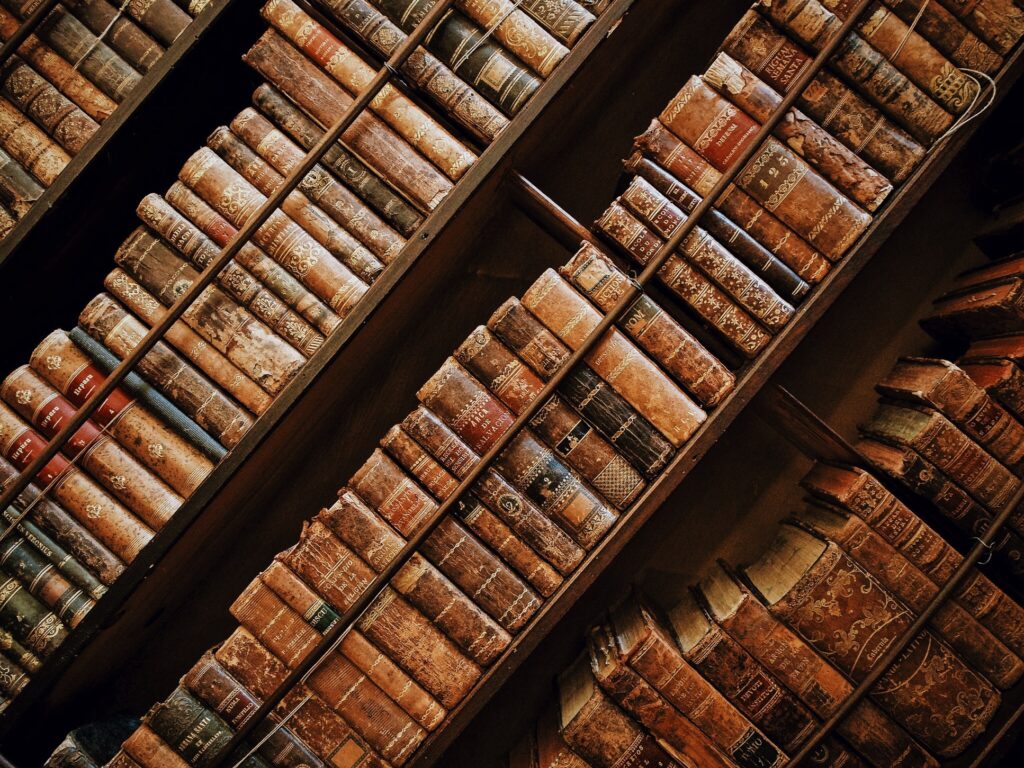
分配可能額とは
分配可能額とは、債権者を保護するために定められた、配当できる金額の上限の金額のことです。
株式会社は、株主総会の決議により株主に対して剰余金の配当を行うことができます。
しかし、株主に対して無制限な配当を行うと会社の財産が社外に流出し、会社の財産的基礎を弱めることになるため、一定の上限を定めています。
剰余金の計算
分配の際に基準となる剰余金は、前期貸借対照表における剰余金に、期中における剰余金の変動を加味した剰余金、すなわち分配時の剰余金です。
前期末の剰余金の額
まずは、前期貸借対照表を元に、前期末の剰余金の額を算定します。
剰余金=株主資本+自己株式ー資本金ー準備金=その他資本剰余金+その他利益剰余金
会社法において、剰余金は「資産+自己株式ー(負債+資本金+準備金プラス株主資本以外のその他の純資産項目)」と規定されていますが、この永算式と「その他資本剰余金+その他利益剰余金」は一致します。
分配時の剰余金の額
分配時の剰余金は、前期末の「その他資本剰余金+その他利益剰余金」を基準い、決算日後に変動した剰余金を加減して算定します。
分配可能額の計算
分配可能額は、分配時の剰余金から次の調整項目を控除した金額になります。
【分配可能額の調整項目】
・自己株式の帳簿価額
・自己株式の処分の対価
・剰余金から控除するのれん等調整額
・その他有価証券評価差額金(借方残高のとき)
更に、純資産額が300万円未満の時や、配当の結果純資産額が300万円未満になるような配当をすることはできません。
のれん調整額がある場合
のれん調整額と資本等金額
のれん等調整額とは、資産の部に計上したのれんの2分の1と繰延資産の合計学を言い、前期貸借対照表にのれん等調整額に該当する項目がある場合、分配可能額算定上、剰余金の金額から減額します。
のれん等調整額を考慮して計算するパターンは、次の4パターンとなります。
【のれん等調整額の計算パターン】
①のれん等調整額≦資産等金額の時
②資本等金額+その他資本剰余金<のれん等調整額≦資本等調整金額+その他資本剰余金の時
③資本等金額+その他資本剰余金<のれん等調整額の時
A.のれん××1/2≦資本等金額+その他資本剰余金の時
B.資本等金額+その他資本剰余金<のれん×1/2の時
※資本等金額とは、前期末における資本金・資本準備金・利益準備金の合計額のことです。
影響額の上限
この影響額は、その他資本剰余金と繰延資産の合計額が上限となり、この影響はのれん等調整額と資本等調整額と資本等金額の大小によって、次のように計算します。
①の場合
のれん等調整額≦資本等金額の時→0円
②の場合
資本等金額<のれん等調整額≦資本等金額プラスその他資本剰余金の時→のれん等調整額ー資本等金額
③ーAの場合
のれん××1/2≦資本等金額+その他資本剰余金の時→のれん等調整額ー資本等金額
③ーBの場合
資本等金額+その他資本剰余金<のれん×1/2の時→その他資本剰余金+繰延資産
関連記事→【 「のれん」資産の落とし穴 】注意点
まとめ
株式投資や経営においても、決算の読み解きは必須になります。
そのため簿記の知識も活かしてより決算書を深く理解しましょう。


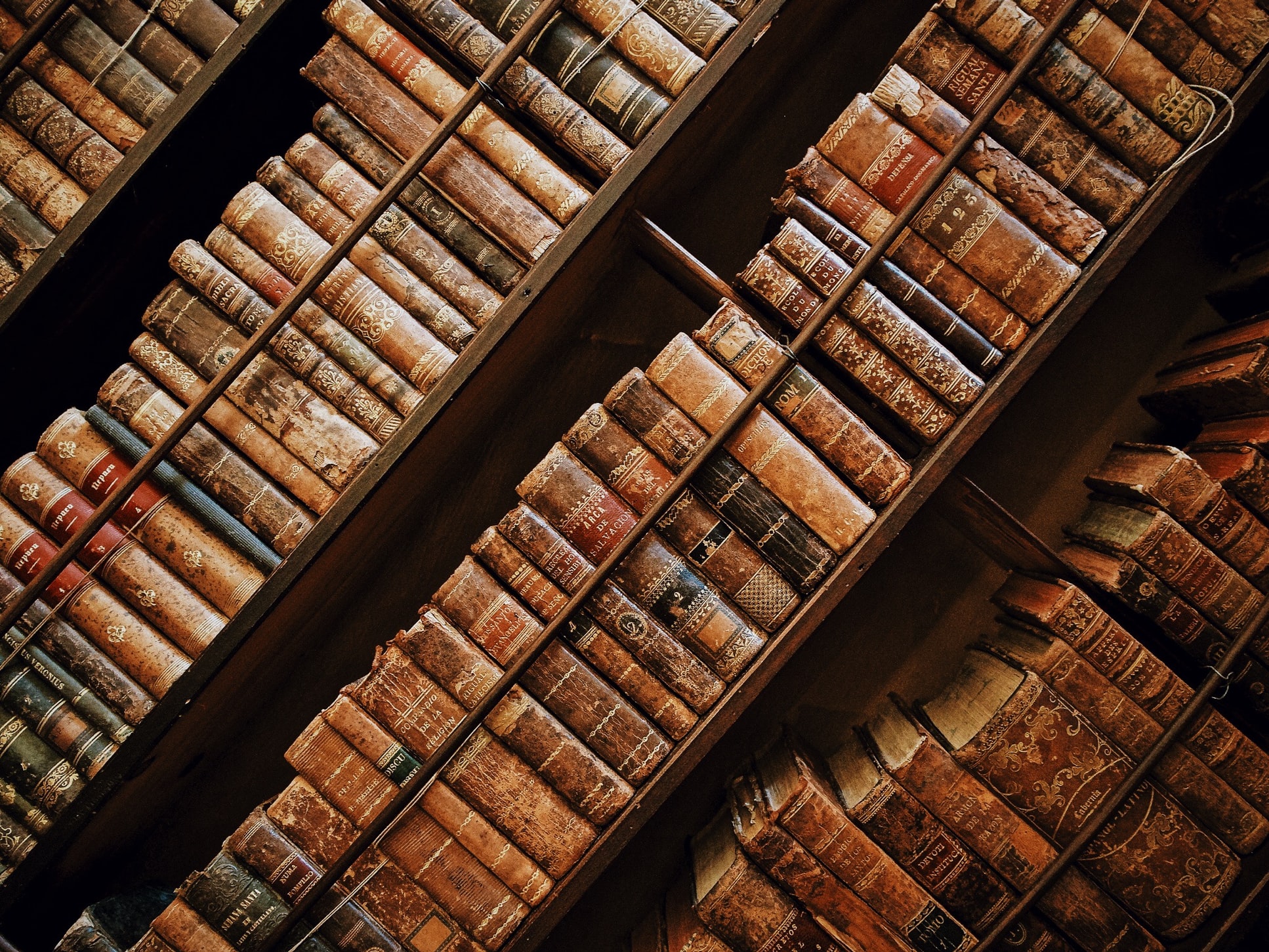

最近のコメント