今回は、「ブランドエクステンション」について解説します。
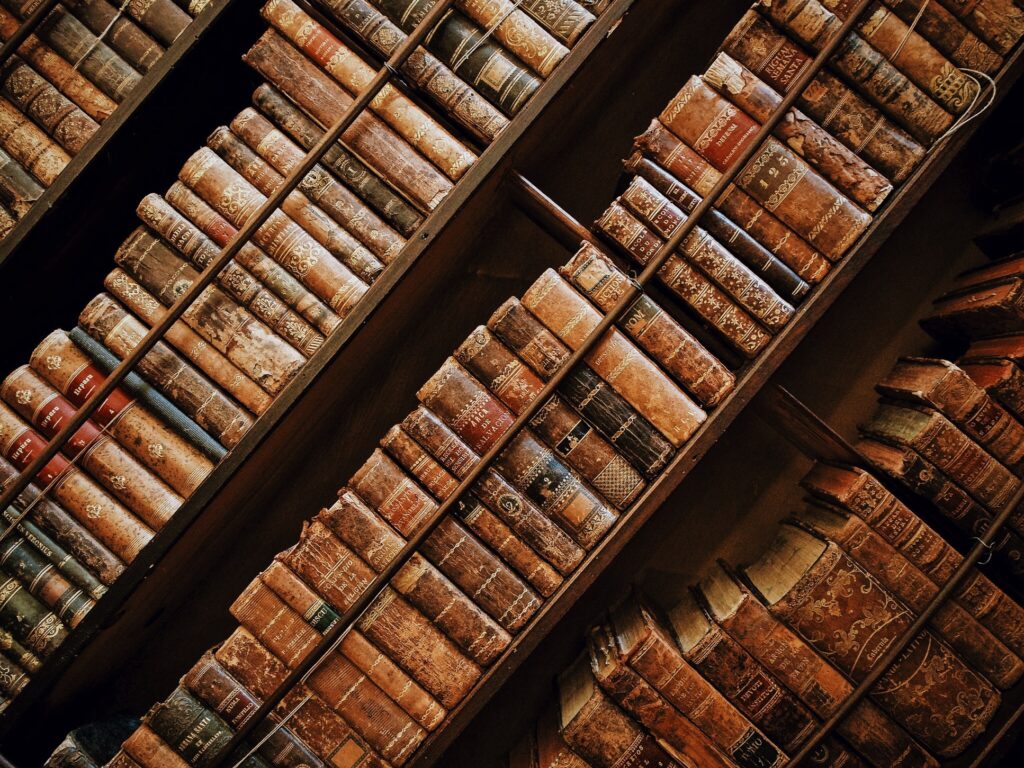
ブランドエクステンションとは
ブランドエクステンションとは、既に確立されたブランド名をそのまま使用して、新しい製品やサービスを市場に導入するというマーケティング戦略において重要な役割を担っているものです。
※ブランドとは→【 ブランドとは 】起源・背景から解説
コンビニストアや百貨店を例に挙げます。
これらの店頭には、毎月多くの新製品が登場しており、私たちの目を楽しませてくれています。
実際、一度購入して気に入った商品が次に店頭にいったときには無くなっているというほど、日本における新製品の投入は目まぐるしく頻繁に行われています。
2005年の新製品投入数は以下の通りでした。
・缶入りコーヒー飲料が213アイテム
・チョコレートは1928アイテム
・セブンイレブンが5300アイテム
・ローソンが6800アイテム
単純計算で毎週100以上の新製品が棚に置いてあるということになります。
このような状況のため、毎回新しいブランドを立ち上げて市場に投入することは、コスト面から見ても難易度が高いです。
だからこそ、既に確立されたブランド名をそのまま使用して、新しい製品やサービスを市場に導入するブランドエクステンションが重要になるのです。
例えば、2004年の米国市場においては、市場投入された1561アイテムの消費財の新製品のうち、94%がブランドエクステンションによるものであるという報告もあります。
ブランドエクステンションの例
ブランドエクステンションによる新製品展開を説明します。
例として、不二家が1964年に発売したブランドの「不二家ネクター」を挙げます。
不二家ネクターは、桃などの果実を裏漉しした甘い味わいが特徴的な、ロングセラー飲料です。
その長い歴史の中で様々なバリエーションによる新製品を市場投入してきています。
そのような新製品には、大別して次の2つのタイプがあります。
| ラインエクステンション | ・異なる果実を用いたフレーバー展開 ・ピーチオレンジやミックスフルーツ ・完熟バナナ・まろやか白桃・つぶつぶ白桃 |
| カテゴリーエクステンション | ・不二家ネクターの桃かき氷(不二家と赤城牛業がコラボして発売) ・不二家ネクターのチョコレート・クッキー・キャンディー |
企業が存続するためには新製品の市場投入は必要不可欠です。
だからブランドエクステンションの利用が必要になるのです。
代表的な手法は、一度構築されたブランドを活用する手法です。
ブランドエクステンションの効果
ブランドエクステンションとは、企業が新製品導入の際に、既に確立されているブランドネームを用いることと定義されます。
このとき、ブランドエクステンションを生み出す元となる既存ブランドを親ブランドと呼びます。
また、新しいブランドが既存のブランドと結びつけられている場合、そのエクステンションはサブブランドとも呼ばれます。
同時に、特定のブランドが様々なエクステンションによって異なる複数の製品と結びついている場合、そのブランドはファミリーブランドとも呼ばれます。
ただしブランドエクステンションは様々な局面に好ましい効果をもたらす一方で、好ましくない効果を派生させる危険も伴うため、注意が必要です。
特に消費者・流通業者・競合他社・自社という4つの視点からそれぞれ説明します。
ブランドエクステンションの好ましい効果
顧客ベースブランドエクイティという考え方をベースに、ブランドエクステンションによって企業にも現れる様々な効果について説明していきます。
ブランドエクステンションの好ましい効果については以下の大きな2つがあります。
①ブランドエクステンションによる新製品は、その導入も比較的スムーズであり、同時に好意的な反応を得やすい
具体的には、消費者は、全く未知のブランドよりも自分にとって馴染みのあるブランドの方が知覚リスクも低く感じます。
それによってトライアル購買を得る確率を上げることができます。
同時に、同じブランドにおいて様々な製品やサービスを展開することによって、消費者のバラエティ・シーキング志向に対応することができます。
例えば、常に多くのフレーバーを展開することによって、消費者の様々な趣向に対応しています。
このように、消費者に自社ブランド内で多種多様な製品を展開させる方法も有効です。
②卸売・小売などの流通業者は、既に確立された名称を使うことによって、流通経路や棚スペースの確保がより容易になることが考えられる
③競合他社は、自社ブランドによる製品を複数展開することによって、ライバル企業からの参入をブロックすることができることが挙げられる
④自社にとっては、同じブランドネームを使用することにより、プロモーション支出やパッケージング・ラベリングの効率化を得たり、導入やフォローアップのためのマーケティングコストを低減させたりすることができます。
また、新しいブランドを開発するのには膨大なコストがかかるため、新しいブランド開発のコスト回避という利点もあります。
ブランドエクステンションによってもたらされる好ましい効果はまだあります。
⑤親ブランドや企業に好意的なフィードバックを得ること
具体的には、まず消費者の視点からは、既にあるブランドの関連製品を展開することによって、新しい顧客層を開拓し市場カバレッジを拡大することが挙げられます。
例えば、トヨタが販売する高級車のレクサスは、比較的低価格な車種まで揃えることによって、ユーザーのすそ野を広げることを狙っています。
⑥流通業者の視点からは、同じブランドネームによる製品を複数展開することにより、親ブランドへの仕入れ依存度を高め、結果として企業の流通に対する交渉力を増加させる可能性がある
⑦競合他社は、自社ブランドを継続的に活用することでよりはっきりと差別化し、親ブランドのポジショニングを確立することができる
⑧自社にとっては、親ブランドの意味を明確化したり、イメージをより好ましい方向へシフトさせたりできる
⑨弱体化したブランドの再活性化を促したり、エクステンションによってそれまでは参入できなかったカテゴリーへも到達できたりする可能性が高まる
例えば、無印良品は、当初は食品など比較的低価格なカテゴリーを扱ったブランドでしたが、次第に生活雑貨・衣類・家具・住宅と、その範囲を高価格なカテゴリーへと拡大してきています。
食品からいきなり高価格な住宅に展開するのには無理があリマスが、衣類や家具などといったカテゴリーを経由することによって、より到達困難なカテゴリーへの展開が可能としていきました。
ブランドエクステンションの好ましくない効果
ブランドエクステンションは様々な好ましい効果を生み出す一方で、企業にとって必ずしも好ましくない効果を派生させることもあります。
具体的には下記です。
①消費者は、あまりに多くの製品やサービスが展開されることによって、彼らがブランドに対して混乱したり、失望したりする可能性がある
過度なエクステンションは不要な選択肢を増やしかねないため、注意が必要です。
②流通業者は、取扱品目の上昇は製品の取引や管理を複雑化させるため、彼らから反発を受ける
ある食品卸が取り扱う松陰の登録情報数は、2002年時点では40万アイテムだったのに対し、2006年時点では82万アイテムにまでは敵わず、食品卸大手3社に夜共同卸の設立へと繋がっています。
②多くのエクステンション商品は小売の棚を圧迫し、店頭管理も複雑になる
③競合他社は、過度なエクステンションが競合他社の更なるエクステンションを誘因し、結果として競争が加速してしまう
また、人や金などの資源の分散ももたらされるでしょう。
④自社は、エクステンション製品の失敗は親ブランドのイメージを損なうことに繋がってしまったり、製品カテゴリーとの一体感を弱めてしまったり、親ブランドが持つイメージの希薄化をもたらしたりすることもある
1991年には、高級服飾雑貨ブランドのグッチが日本市場で販売する商品数を前年よりも4割削減しました。
あまりにも多くの衣裳品を抱えてしまったブランドは、結果として安い価格帯のカテゴリーにまで拡張してしまっているケースが多いです。
そのような場合、ブランドが持つ高級なイメージを維持することが困難になってしまいます。
また、ブランドエクステンションは有効な戦略である一方、全く新しいブランドを開発する機会を逃してしまう点も重要である。
ブランドエクステンションの効果まとめ(表)
以上をまとめたものが下の表です。
| 消費者 | 流通業者 | 競合他社 | 自社 | |
| 好ましい効果 | 知覚リスク低減・トライアル機会上昇・バラエティシーキング機会の提供・新市場開拓・市場カバレッジ拡大 | 流通経路確保・交渉力の拡大 | 競合他社のブロック・差別化によるポジショニングの確立 | プロモーション支出やパッケージング。ラベリングの効率化・マーケティングコスト低減・新ブランド開発コスト回避・意味の明確化・イメージ強化・再活性化・更なるエクステンション機会の獲得 |
| 好ましくない効果 | 混乱や失望 | 取引や管理の複雑化・反発・棚の圧迫 | 競争の加速・資源の分散化 | イメージ低下(成功・失敗)・カニバリゼーション・カテゴリー体化低下・意味の希薄化・新ブランド開発機会損失 |
ブランドエクステンションの種類
ブランドエクステンションには、大きく分け2つのタイプがあります。
| ラインエクステーション | ・親ブランドと同一の製品カテゴリーにおいて、親ブランドを用いて新製品を導入することを意味している |
| カテゴリーエクステンション | ・親ブランドとは異なる製品カテゴリーに親ブランドを親ブランドを用いて新製品を導入することを意味している |
それぞれ説明していきます。
ラインエクステンション
ブランドエクステンションにおいては、ラインエクステンションは圧倒的にカテゴリーエクステンションよりも頻繁に使用されることが知られています。
このことは、新ブランドを市場に導入するよりもラインエクステンションは開発期間が半分になり、導入コストも大幅に減少し、導入した製品がより成功しやすいという報告とも整合的です。
企業がラインエクステンションを採用しやすい傾向にある理由について説明します。
1番の理由は、多様化する顧客ニーズへの対応という問題にとって、ラインエクステンションが相対的に低コストかつ低リスク対処法であるということです。
例えば、個々に分散したセグメントに迅速かつ効果的に対応するために、菓子メーカーや飲料メーカーは様々な味の製品展開を季節ごとに行っています。
また、消費者のバラエティシーキング志向に対しては、様々なラインエクステンション製品を投入し、親ブランドが幅広い製品ラインを抱えることも重要でしょう。
これによって、企業の価格戦略にも幅が出ることが期待できます。
親ブランドよりもより高価格帯や低価格帯に製品を展開することを垂直的エクステンションと言います。
例えば、iRobot社による自動掃除機ロボットのルンバが、機能を縮小したより安価なエントリーモデルを市場投入したのがその例です。
また、様々な紫衣品を市場に投入するにしたがい、既存の生産ラインにも余韻が出てくることが予想されます。
しかしラインエクステンションはこのような生産設備を効率よく稼働させることができます。
また、比較的低レベルのリスクで高いパフォーマンスをもたらすため、特に短期的な利益を生み出しやすいということも理由の1つです。
競合他社への対応という視点からは、頻繁なバリエーション追加によって他社の棚を奪ったり、価格レベルを維持して参入価格を高めたりするという理由もあります。
ラインエクステンションの注意点
まず過度なラインエクステンションは個々の製品の親ブランドラインにおける役割を不明瞭にし、結果として全体の混乱をもたらすリスクがあります。
また、消費者にとってはたくさんのバリエーションが同じ親ブランドの名前の下に展開されるため、特定の製品に対するロイヤリティが低下するリスクもあります。
更に、安易なラインエクステンションによって、新しいブランドを立ち上げる機会が喪失されるリスクもあります。
そのため親ブランドが展開する製品カテゴリーにおける消費量については、ラインエクステンションによって消費が刺激されたとしても、早々増えるものではないことにも注意が必要です。
結果的に、特定品目への売上の集中という非効率的な状況に陥ってしまうこともあります。
ラインエクステンション製品が角にあることによって、小売段階における棚スペースの圧迫も企業からすると痛いです。
最後に、コスト予測の難しさがあります。
ラインエクステンションによる直接的なコスト上昇はある程度予測できるかもしれません。
しかし、ブランドイメージの希薄化・生産ラインに生じる負荷・物流段階やサプライヤーに対する対応の調整などといった要因からもたらされるコストについては、予測が難しいです。
したがって、ラインエクステンションの実施には、長期的なコスト変化の注意が必要です。
カテゴリーエクステンション
カテゴリーエクステンションは、ラインエクステンションほど頻繁ではありません。
親ブランドとは異なった製品カテゴリーに新製品を展開するカテゴリーエクステンションも、新たな顧客ニーズを捉えて収益をもたらす可能性が高いです。
※ブランドのカテゴリーについて→ブランドの【 カテゴライゼーション 】分かりやすく解説
そのため、実務的な関心も高くなります。
新しい製品市場へのブランドエクステンションの効果は、異なる製品のカテゴリーに特定のブランドが展開されている場合、消費者への露出機会も高まり、そのブランドのイメージを高めることが期待できます。
また、既に力を失いつつある親ブランドを新規の製品カテゴリーに展開することによって、ブランドア全体の再活性化を行うこともできます。
つまり、異なるカテゴリーに展開することによって、親ブランドの持つイメージを好ましい方向へ変更することも可能ということです。
カテゴリーエクステンションにおいては、ラインエクステンションよりも大きな変更を伴った新製品が投入される可能性が高いです。
しかし、一連のカテゴリーエクステンションによって蓄積された製品群は、一定の製品カテゴリーにまたがる親ブランドを、全体としてどのように方向付けてゆくか事前に十分な検討を加えることです。
親ブランドの最終的な製品範囲についての明確なビジョンを持ち、当該ブランドを長期的に管理することが必要不可欠となってきます。
カテゴリーエクステンションの注意点
ここからはカテゴリーエクステンションにおける注意点になります。
ある製品カテゴリーの典型的な雛形と見做されているブランドは、それ以外の製品カテゴリーに展開することが困難な場合があります。
例を挙げます。
元々絆創膏を製造していたニチバンが1948年に登録商標として市場導入したセロハンテープは、様々な広告を駆使した結果、高い知名度を獲得し普及しました。
消費者にとっても、文具における接着テープとしての認知が極めて高く、結果として製品カテゴリーの代名詞的な存在となっています。
しかし、強固なイメージが定着してしまった結果、セロテープブランドによるペンやクリップなどは、同じ文具だとしても違和感があると感じとられる可能性があるということです。
また、オリジナル製品においては肯定的に捉えられていた連想がエクステンションの結果として導入されたあたらしい製品のカテゴリーにおいては否定的に捉えられてしまうこともあります。
まとめ
ブランドエクステンションでは、既に確立されたブランドを用いて、新しいサービスや製品を導入することです。
効果は、上で表にまとめたものが最もわかりやすいです。
そして、親ブランドと同一の製品カテゴリーにおいて親ブランドを用いて新製品を導入するラインエクステーションと、親ブランドとは異なる製品カテゴリーに親ブランドを用いて新製品を導入するカテゴリーエクステンションを使い分けます。
それぞれに注意点がありますが、既に消費者から強固なブランド概念が想起されている場合は、派生する商品もそのブランドのイメージに沿わせないと、大元がコケてしまうリスクがあるということです。
最近では、シャネルがYoutubeコムドットさんを新製品のCMとして流したことにより、ブランドイメージの混乱が怒ったことがありましたね。
私はコムドットさんについて知識がないためなんとも申せませんが、このブランドイメージが話題になったことは周知の事実でしょう。
そのため、ブランドのイメージ維持・向上とは逸れた事をすると、既存の顧客も離れるというリスクがあるため、既存のブランドから新しい物事を発展させる場合は、長期的なブランドイメージを重視して慎重に考えましょう。
関連記事→マーケティングにおける【 ブランドビルディングブロック 】分かりやすく解説


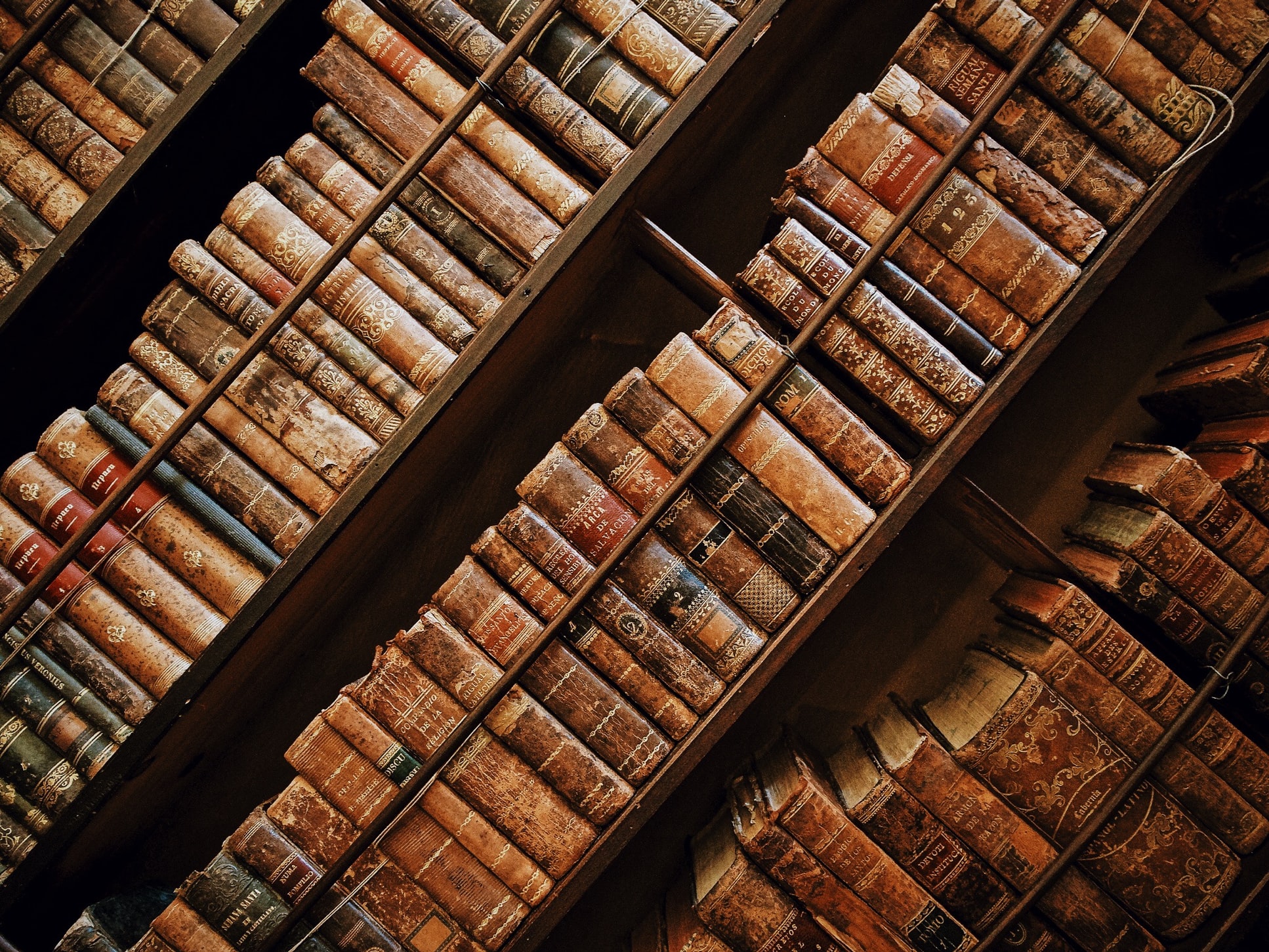


最近のコメント